現代文語彙14
2007年度本試験評論問題から
「不変の形を作り出すことが芸術の本質なら、変化を生命とする日本の庭はおよそ芸術と言えるかどうか。」

この問題文で指摘されている「日本の芸術のあり方」を考える前に、私たちが共通して持っていると思われる「日本人の自然観」に触れてみたい。松下幸之助と言う人の名前をご存じだろうか。松下電器いや諸君にはナショナル電気あるいはパナソニックといった方が良いのかもしれない。パナソニックと言う会社の創始者の方だ。この方が経営の秘訣について「天地自然の理法に従って事をしていることだ」と言っておられる。このように人生観や世界観を述べるとき自然という観念に拠り所を求める人が日本人は多い。世界と自己との関係にゆがみや矛盾があれば不自然であり、調和していれば自然と感じるわけだ。

ところで、この「自然」という語が「natureネーチャー」の訳語として使われ出したのが明治以降であることをご存じだろうかそれ以前は「じねん」と読み「おのづから」という意味の形容詞あるいは副詞として使われている。「現代の自然・ネーチャー」にあたるものは「天地・造化・山川草木」と呼ばれていた。ネーチャーを表す言葉が無かったと言う事実は、日本人が「自然」を自分と切り離したものとして見ていなかったことを表している。よって自分の住む世界・社会は自然の延長線上にあるものとし捉え、「社会」を創り上げるべきものとして考える意識が弱いとも言えよう。

ヨーロッパ的な発想では「社会とは人間が意図的創り上げたもの」である。そこに弊害や矛盾があれば改良していくべきものとなる。当然、人間の創り出す文化も自然と対立したものとなる。伝統的な日本家屋が、縁側があって外の自然に開かれているのに対して、西洋建築は外界との境は壁によって閉じられている。

もう少し、別の観点から日本人の自然観を考える。「藁葺きの屋根の農家・夕日に照らされた赤い柿の実をつけた木のある風景・家の屏風に描かれた小雨が煙るように見える桜の吉野山」「桜咲く吉野」というもっとも美化され理想化された造形なイメージを日本人はこよなく愛している。名所旧跡や常套的と思えるものの取り合わせ、季節の様々な景物が屏風や装飾画にかれる。目に映ったものを忠実に再現する西欧的な写実的技法とは無縁である。風景を「もの」としては眺めない。主体が体験する、いわば「出来事」として眺める。桜は「こうあるべきだ」と言った理念をイメージ化しようとする。
季節は日本の伝統的文学・美術において重要な位置を占めてきた。「自然は季節において、刻々と変化しつつも、欠けることなく充満した姿を見せている。人間は自然の中の一つの存在として、この自然の中にいる。」
普段、諸君も気づかないまま過ごしているだろうが、私たちは日々の生活の背景としてある日本文化の中で、知らず知らずのうちに、ある特定の感性のスタイルを持たされているのだ。「暗夜行路」の主人公は「疲れ切ってはいるが、それが不思議な陶酔感となって感ぜられた。彼は自分の精神も肉体も、今、この広大な自然の中にとけ込んでいくのを感じた」としている。単に美意識としての風景という次元を越えて、自然は私たちの深部にあり、私たちを支えてすらいるかもしれない。「不来方のお城の草に臥ころびて空に吸われし十五のこころ」啄木のうたである。
さて「芸術」に話をもどそう。「芸術」は学問(科学)や宗教と並ぶ「人間の知」の一つであると言われている。ローマ帝国が広がるにつれてキリスト教が広まり、神の代理人としての教会がヨーロッパ世界を支配した。人々の間には宗教を通して明確な世界観(人間が世界をどう見るか)が共有されることとなる。芸術は、宗教画や宗教音楽と言う形で「完全なる神の世界」を象徴的に描くものであった。
近代となり、神の束縛から解放され、個人として自由に活動するようになって「芸術」の働きは変わったのだろうか。科学が近代の豊かさを生み出したことは間違いない。が、科学は完全なものではない。「命とは何か。愛とは何か。」を科学は説明できない。科学は自然の普遍的な法則を明らかにしようとした。しかし人間の理性を駆使しても、きわめて不自然な形でしか、部分的なものとしてしか、命や愛や世界を示せなかった。それを補い普遍的な世界、全体的な姿を明らかにしようとして「芸術」家は今も模索していると言えよう。
「自分一個のはからいを極微にとどめる」
「座の雰囲気の純一化」
「自己を没却し、自然のままに随順し、仲間と楽しみを一つにする」
「作者の個の表現としての作品を重んずる近代風の考え・ヨーロッパ風の芸術理念」
「造化に随うという東洋古来の理念」

上記の複数の表現に見られる「全体と個の表現」について考えてみたい。まず「茶碗」の美について考える。この陶器は無名職人によって日常の用のために作られた雑器である。職人たちは美を作ろうとしたのではあるまい。積み重ねられた長い伝統と、くり返された長い経験が器を作り出した。いわば無造作な自然な心が彼らに美を作らせたと思われる。職人たちは自己を高めようする西欧の芸術家のあり方とは逆に自己を無名にすること、自己の存在を低めようとしている。低めることで自己と世界のありが見えてきたのではないだろうか。自己を低めることは、世界に対し、自然に対し敬虔な心を抱くことであり畏れを持つことである。その心が「器の美しさ」を巧まずして生み出す。
さらに日本の芸術家にとって自然は表現の対象であるにとどまっていない。芸術作品に最後まで責任を負うのが西欧の芸術家であるなら、日本の芸術家は、その作品の完成を自然と歳月の手にゆだねる。碗を焼き上げる竈の火加減や、庭園の石の苔や塀の染み汚れが作品の完成に手を貸す。職人たちは、その先の一瞬のいのちの輝きを得ようとしているとも言える。

連句の集団による作品制作の場における芭蕉は言わば指揮者である。日本的なリーダーは場を調する世話役タイプが良いとされ、たとい能力があっても、それに頼らず無為であることが理想とされる。自らの力に頼るのではく、全体のバランスをはかることが大切であり、必ずしも力や権威は必要とされない。連句としての前後のつながりを含めて作品であること、複数人で続けて句を詠みあうという表現の性格から、作り手と受け手が同一空間にいる必要のあった俳諧の連歌の宗匠としての芭蕉は、まさにこのタイプのリーダーであったろう。
先に日本人は自然と連続的な意識を持つと書いた。同じように、日本人が自分の属する集団と連続的な意識の中で生きようする傾向を持つことを指摘したい。インディビジュアルという語に「個人」と言う翻訳語をあてることが定着したのは、これまた明治の十年代の後半らしい。この語に相当する言葉がなかったのだから「個人」という意識は人々の間に生まれていなかっただろう。
さて諸君は「人」を単位としてではなく、その「所属」で見てはいないか。目の前の先生をどう見ているのだろうか。先生の考え方や感性よりも出身大学がまず気になるのではないか。自分の属する集団だけでなく、相手を相手の属する集団の中の一員として、まず捉えようとする傾向があることに気づいてほしい。
名刺では、名前より勤め先や役職がその用紙の大きな場所を占めている。普段の生活の中で諸君は、自分の所属する集団における先生やクラスの生徒の非難や嘲笑を恐れて、他者の目を常に意識して自分の行動をコントロールしているに違いない。誰も見ていなかったら、何でもやるという人もいるようだ。アカの他人にはどう思われても良いが、世間体は大切にする。

今も個人単位で人間を見ないという点では同じであると言えそうだ。ヨーロッパの学校では先生から命令されても、自分の理性に照らして納得できない場合は、先生の指示であっても拒否する場合があると聞いた。日本の学校では個人の判断は、たとえ理性による的確なものであっても、個人的な判断であり、わがままと見なされる。
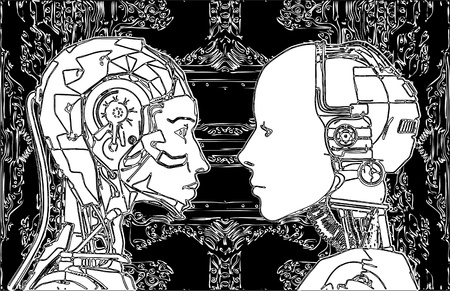
私たちの行動をコントロールするものの一つに本能がある。普段の私たちはもう一つの私たちをコントロールするもの、「自我に基づいて行動をしている。自我とは、「本能以外のもので、行動をコントロールする内部的な規範のこと」であるが、日本人の自我は孤立的なものではなく他との交流を通して形成されると言われている。相互依存・相互信頼を基本とする。
君たちは他者との関係において一人称を使いわけているはずだ。大人と接するときは、自分を「僕は・・」と表現し、友達と接するときは、自分を「俺は・・」と表現している場合、明らかに相互関係を機軸にしていることがわかる。このことは、他者のあり方から自分のあり方を検討する内的コミュニケーションを発達させてもいる。個性を演出したいのなら、ピンクやブルーの髪型やズボンをはいてもよさそうなのに、そろって君たちは茶髪・短いスカートを選択する。家族においても、その一人一人は独立した個人意識を持たず、家族という集合の中でまとまっている。その家族に対する意識は家の構造にも反映されている。隔てのない家族の間柄は、襖や障で仕切られただけの鍵のかからない部屋によって象徴されている。

個人意識を重視する西欧の家屋は個々別々の部屋に仕切られ、それぞれの部屋が鍵を持つ。日本家屋では玄関で靴を脱ぐ。家と外は明確に区別されている。西欧人が部屋から出れば、たとえそこがリビングであろうとパジャマ姿でくつろぐところではない。ホテルの廊下を浴衣姿で歩く日本人に対し怪訝な顔を外国の方が向けるのは当然なのだ。